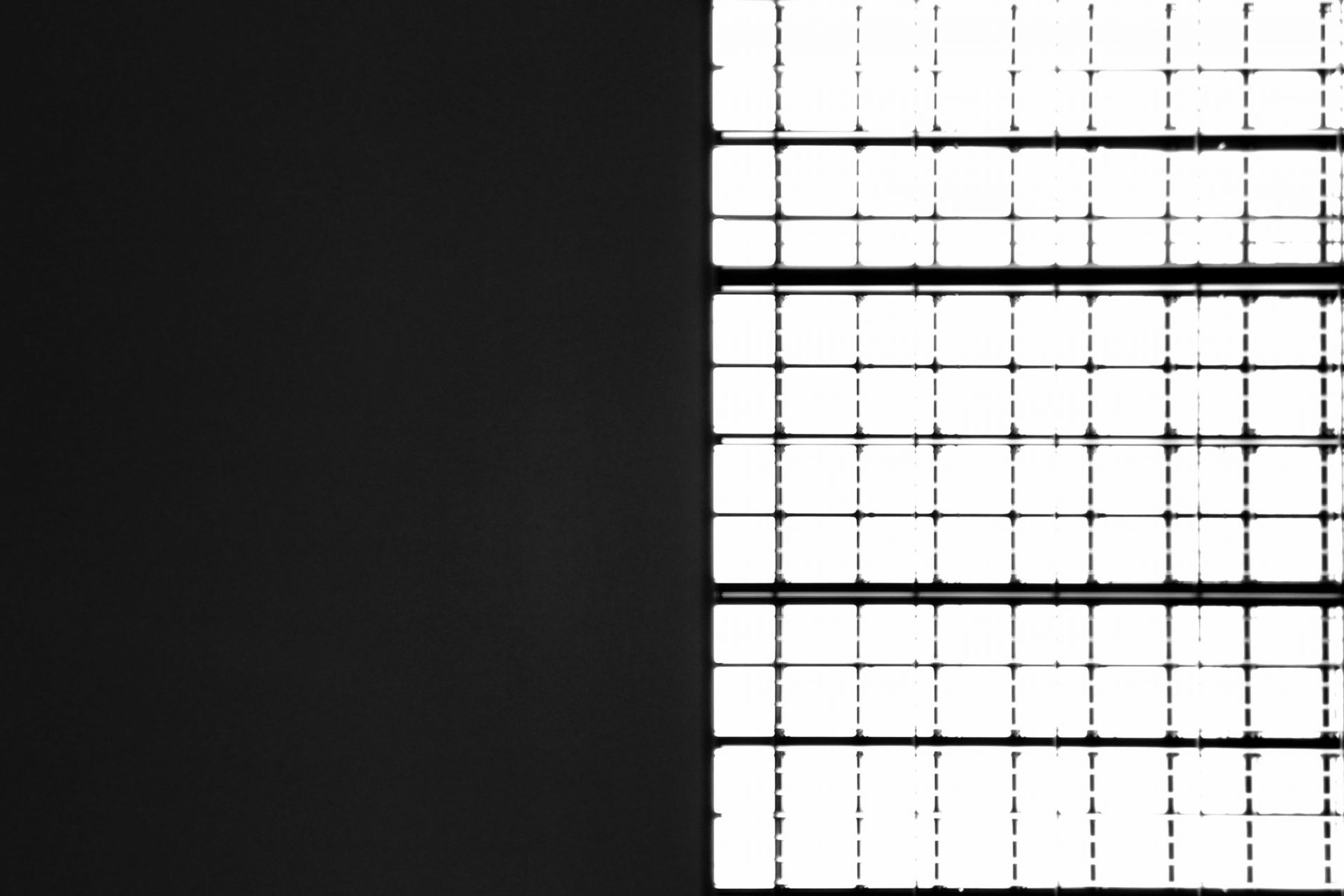法事から帰宅して遅めの昼食後に薬を飲んだら、薬の作用で眠くなって午睡。そしたら意味の分からん夢を見た。まぁ夢なんて意味分からないのが多いが、最近はあまり夢を憶えてないので印象が強烈。
=====
仕事終わりか何かだろうか? 荷物を持ったボクは、数回は訪れた事があるけれどもそれほど馴染みのない街にいる。その街がどこなのか特定できないが東京である事は間違いない。なぜなら「遅くなったらタクシーで帰ることができる」という安堵感があったからだ。見知らぬ街と馴染みの街の間くらいの街で、ボクは家路を急いでいるわけではなく、約束があるわけでもなく、なんとなく歩いている。
すると路地裏にある1軒の古びた店が目に入る。4人掛けのテーブルが2つ。あとはカウンター。街の洋食屋といった風情だがそこは単なる洋食屋ではないことは知っている。何回か通った事があるのでマスターも知らぬわけではない。その店には常連しか知らない秘密の暗号みたいなものがあって、マスターにそれを伝えないと洋食を作ってもらえないのだ。
洋食を作ってもらえないとどうなるのか? 暗号を知らない客は、その店の自家製ピクルスを当てにウィスキーを呑むしかない。それがこの店の暗黙のルールなのだ。しかしこのピクルスが非常識に旨いので、それはそれで嬉しかったりもする。
暗号を知っていて洋食を作ってもらえると、この店の秘伝のデミグラスソースのタンシチューを頂く事ができる。黒に近い色にまで煮込まれた褐色のデミグラスソースは、塩気や旨みや香りがほとんど感じられないのに、ひたすらにコクがある不思議な味がするのだった。
数年ぶりだろうか。
その店の扉を開けると、全く知らないマスターと全く知らない客がいた。店の内装も変わっていて、そこはまるで知らぬ店だった。
ちょっと違和感を覚えたけれども、空いていたカウンターの一席に腰を下ろし
「すいません。ウィスキーをロックで」
と注文をした。これがこの店のしきたりなんである。すると店の空気が一瞬固まって、みんながそのままの方向を見たまま耳だけをこっちに傾けた。満席とはいえ10人も入ればいっぱいの店だ。お酒と食事で賑やかではあるが居酒屋の大型店舗とはわけが違うので、客の話し声が途絶えるとボクとマスターのやり取りが店中に筒抜けになる。
前のマスターと同じくらいの年齢だろうか。ボクよりも10歳以上は上に見える新しいマスターが
「かしこまりました」
とだけ言った。
そのやり取りに安堵したのか、こっちに注目していた他の客たちも、再びお酒を呑んだり、食べたり、お喋りしたりを再開した。店はボクが来る前と同じ感じになった。
…と。
店の奥から1人の男がこちらに近づいてくる。どこかで見た顔だ。
どこかで見たというより面識がある。仕事関係の繋がりか? 背広を着ている感じから推測するに遊び関係の繋がりではなさそうだ。
しかしどこで会った誰なのか、咄嗟に思い出す事ができずにいると
「いやー。お越し頂いて光栄ですよ」
と、その男がボクに握手を求めてきた。
相手が誰なのか思い出せない失礼を悟られないように、ボクは適当に
「ごぶさたしています」
と相槌をうった。
「忙しいと聞いてたので、今日はムリかと思ってました」
なんて答えたらいいのか迷っていると
「はい。ウィスキーロックです」
と、マスターがウィスキーを出してくれた。しかも当てとしてピクルスがついている。
「せっかくなのでピクルスをどうぞ。来てすぐに申し訳ないですが、時間もないのででましょうか」
と男が言った。
なんだか分からないままにボクはウィスキーのロックを飲み干した。
ウィスキーが咽から胃に落ちると、白黒だった世界に、すっと色がついた。
ピクルスを噛ると、なんだかとても不味くて、ピクルスの味まで変わってしまったことが悲しい。
「さぁ、行きましょう」
と促されて、ボクはその洋食屋を一緒に店を出た。
その人が誰なのか、どこに行くのかもさっぱり分からない。
しかし空腹に呑んだウィスキーがじんわりと効いてきて足取りは軽かった。
つづく